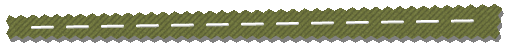
| あとから書いたプロローグ 宮崎駅のプラットフォームに降り立った時、存外の寒さを私は感じていた。六月も半ばを過ぎようとしていた頃であった。 仕事、いや広島での生活すべてに行き詰まりを感じていた私には、とにかく広島をしばらく離れてみることが必要だと言う気がしていた。 現実を離れれば現実を客観的に見ることができるのではないかと思われた。 行き詰まったとはいえ企業活動の第一線に立つ身であり仕事に追われていたのではあるが、半ば強引に要求して無理やり一週間の休暇を得たものの、私ははたと考え込んでしまった。 一週間、何処かの温泉で湯治三昧にふけるほど私は経済的におおらかではない。 旅に趣味がない私の行くところは奥能登の生家か、宮崎――広島に赴任してからはたびたび訪れた母の実家――しかない。 そこにはかって一人の異性として想いを寄せた従妹がいる。 それはもう傷口のふさがった古傷ではあったけれど。私は一年前、彼女に別れを告げているのだ。 二度と宮崎には足を踏み入れないと。 結局私はいつものように宮崎に行くことにした。 何回も鉄道を乗り継がなければならない奥能登とは違い、宮崎へは急行青島一本で広島から直行できてしまう。 メンツはつぶれるが、そんなことは知らない、いや知っていたとしても叔母達はいつものように歓迎してくれるだろう。 古傷に触るのはあまり面白くないが、絶対触るべからざるものでもなかろう。 いや、触って見なければ完全に癒えたかどうか判らぬではないか。 完治したという自信はあるし、理論的にも裏付けがある。 この一年は傷の治療に費やしたしともいえるし、恋愛の構造もほぼ解明できた。新たな恋さえ経験した。 それに従妹はバスガイドと言うその職業上、必ずしも宮崎にいるとは限らないから顔が会うかどうかは判らないし、会わせなければならぬ用事も必要もない。 あくまで自分を見つめるために広島を離れるのだ。 こうして私は一年ぶりに宮崎の地を踏んだ。そこはもう自分を招く安息の地ではなくなっていることをとっくに知っていながら。 従妹と私は一つ違いで、母のすぐ下の妹の次女として生まれた。 祖父が亡くなったとき初めて会い、仲良く手をつないで写真にも写ってはいるが、私が四歳のときでありまったく記憶にはない。 事実上の出会いは私が二十歳の秋に祖母と私より一つ上の従姉と三人で奥能登を訪れたときである。 もっぱら接待役立った私は祖母を一人にしたくなかったが為に結局何をも為し得ず、内心申し訳なく思って気ばかり使っていたところへのんきな従妹は人の気も知らず 「あ〜あ、退屈だなあ。」 と独り言をのたまわって私の心をぐさりとえぐったものである。 退屈しのぎにみんなで栗拾いに連れて行き、そろそろ帰り時だと思って 「もうそろそろいいかな。」 と声を掛けると、私の期待した答えとはまったく別の、遠慮のかけらもない 「まだ!」 と言う返事が帰ってきた時は能登にはいない種類の子だと驚いた覚えがある。 この時はまだちょっと太目の、おかしな親戚の女の子、というだけだった。 私が従妹を女性として見たのは就職して最初の挫折で宮崎を訪れたときからである。 限りなく楽天的で明るい従妹はきれいだとはとても言えないにしても南国の太陽のような娘で、私の心をずいぶん明るくしてくれた。 妹のいない私にとって可愛い妹であり、ややままごと的ではあるが恋人でもあり、たわいもない手紙が行き交うようになった。 従妹は観光バスのガイドをしていて、私も二度、定期観光バスに乗ってその迷ガイド振りを見、冷や汗を流した。 台本の文句は忘れるし、質問などで台本にない話になるとすぐ宮崎弁が出てしまうし、八方破れのガイド振り、それがけっこうお客には受けていて本人はしゃあしゃあとしているが、私やいっしょに乗ってみた彼女の母である叔母は、笑うどころではなく恥ずかしくて顔もあげられなかった。 定期観光バスに乗っていた頃は夕方になれば必ず宮崎交通本社に帰ってくるから、私はよく本社前の発着所でバスの到着を待ったものである。 だんだん経験が増えるとともに貸切バス乗務になると宮崎にいっても会えずに帰ることもあり、会えぬということがさらに私の想いをつのらせることにもなったが、そういうすれ違いと私の意地っ張りがもとでけんかをし、手紙も途絶えた。 その時から長い苦しみが始まることになる。 愚かな私は自分の持っていたものがどんなに大切であったか失うまで気が付かなかったのである。 そして気づいたときはもう遅かった。 謝罪の手紙にも返事がなく、直接詫びるにも会ってはくれなかった。 広島と宮崎へ600キロ、日豊本線の急行で10時間、夜行で行き、夜行で帰る辛い旅を何の実りもないまま繰り返した。 かってはこの世で最も美しいと思った空も山も水ももはや私を歓迎してはくれなかった。 私を迎えてくれるのはいつも留守番をしている祖母だけだった。 私は夜となく昼となく宮崎の街を彷徨いいるわけのない人を人込みの中に追い求めるのだった。 宮崎の街はいつも微笑んでいる。 しかし私はその微笑の視線が誰をも見ていないことに気がついた。 人は皆、その作り物の微笑を見てそれが自分のものだと思い込んでしまうのだ。 それは観光の街の生きるが為の媚であり悲しい性(さが)であろう。 私はその視線の外でその視線を追い求めながら、宮崎という名に含まれたものすべてと、従妹という一人の女との間に境界がないことを知り始めていた。 半年、ずいぶんと長い半年の間に私の想いは或いは歪んでしまったかもしれない。 私は自分の若さも知っていたし、経済力も長男たる自分の立場も忘れていたわけでもないはずであるが、従妹を永久に失うことの恐怖に耐えかねて憑かれたように求婚の手紙を書いてしまった。 それは最初から絶望的でしかなかった。 当時もし承諾の返事があれば仕事も家も捨ててすぐ宮崎に飛んでいくつもりではいたのだけれども冷静に考えてみれば全く不可能なことなのだ。 成人式を終えたばかりの娘は私よりもずっと冷静であったことだろう。 「誰よりも ばあちゃんを愛している。」 と答えてきた。 絶望しかない時代であった。 何の喜びもなかった。 傷の痛みにのたうち回り、こらえようとして何にでもすがった。 合唱、ギター、スキー、写真、ラグビー、旅、そして女。 人はそんな私の生き方を充実していると言った。 充実した人生とはそんなものかもしれない。 空白の時を持つことが怖いために何かで埋めようとする・・・空白の時間は傷の痛みを思い出させるから。 私はそれでも待つ気でいた。 いつか従妹の戻ってくるのを。 しかしこの頃から潜在意識の中では従妹そのものを忘れようとする努力が始まっていたに違いない。 いわば自己保全の本能的志向として。 私が自分の意志で忘れようと思い始めたのはずっと後になる。 忘れようと思い立つまで私は感情の支配下にあり、感情の主たるものは嫉妬、それも不特定多数に対する嫉妬だったように思える。 苦しんだのは結局愛想のものより嫉妬であったのかもしれない。 私が従妹との結婚を断念しようと決心した時、すなわち理性を取り戻したのは再び電話が掛かってきたり、手紙が届いたりしていくらか結婚が現実味を帯びてきてからである。 結婚すればおそらく子供ができる。 いや作るであろう。 欲しくなかったけれどできてしまったという場合にしろ、子供が欲しくて作ったにしろそれは親の欲望だけでしかない。 とすれば親は子の存在に対して全責任を持たなければならぬはずである。 五体満足な私でも親を恨んだこともあるし、少なくとも生んでくれたことに対して感謝したことはない。 まして生まれてきた子供がもし業を背負っていたとしたら親はどうやって償うのか。 あまつさえその可能性の強いことを知っていたとすれば。 好きだから、と言うことがすべてに優先することが許されるのだろうか。 私の理性は長い割当の末、ついに感情を制し結婚は否、と言う判定を下した。 そしてこのときはっきり従妹を忘れようと決心したのである。 そんな思い出も今は遠いものだった。 私は空白時間を持つために宮崎に来ている。 ところが三日目に、以前のいきさつは多分承知の従姉がせっかく帰ってきた(宮崎の人たちは私が行くと帰ってきたと言う)のだから、とおせっかいにも従妹に電話を掛けた。 従妹はちょうど非番だからすぐ帰ると言う。 幸か不幸か古傷に古傷に触ってみることになった。 宮崎市内から高鍋の母の実家までほぼ一時間、結局今までの通り、帰りを待つことになってしまった。 来るか来ないかわからぬ人をひたすら待ったかっての思い出が生々しく甦ってきた。 それは今の私の誇りを著しく傷つけた。 「俺はおまえに会いに来たのではない。」 私は自尊心に追われて家を出た。 長い間小丸川の堤防に座っていた。 昔、奥能登出身で陸軍航空隊の青年将校であった父と宮崎の娘であった母もこの川を共に眺めたに違いない。 二十余年後その息子は生きることに戸惑って同じ川のほとりに座っている。 私は小丸川に流れ込む小川を見ていた。 元来私は水の流れを見つめることが好きなのだ。 上流から流れてきた木片などが堰を越え、渦に巻き込まれて流去ると思えばまた戻され或いは沈みまた浮かびついには渦を抜け出すところが面白く眺めていると時間を忘れるのが常である。 気が付くとすでに家を出てから一時間は軽く過ぎていた。 もう帰っているだろう。 私はおもむろに立ち上がった。 ことさらゆっくり歩きながら何を話すべきか考えた。 近況、この先のこと、それから、そうだ、ガイドを辞めさせなければならぬ。 ガイドという職業は従妹の天真爛漫な心を少しずつ蝕みつつある。 何はともあれ、本人の幸せのためにはガイドを辞めさせるのが先決だ。 そうすれば結婚相手もすぐに・・・とそこまで考えて思わず苦笑が漏れた。 かってあれほど嫉妬に苦しめられたのに結婚相手の心配までするなんて。 家の手前、数メートルで一台のタクシーが私を追い越した。 従妹であった。 十分間ぐらいは・・・持ったような気がする。 話の中で何かの嫉妬がポツっとにじんだような感覚があった。 これはまずいな、と思うまもなく一年余掛かって築き上げたものがあっという間にガラガラと音をたてて崩れた。 癒えた筈の傷はパックリ口をあけて鮮血を噴き出したのである。 従兄妹同士ゆえに巡り会い、従兄妹同士ゆえに成就してはならない恋、私は自分の罪の深さ、罰の重さに絶望のどん底へと再び突き落とされた。 次の日には別府への仕事があるからと宮崎へ帰って行った従妹をいつものように縁側で見送ったあと、私は魂の抜け殻のようになって庭先に咲くカンナの花を見つめていた。 血のように赤いその花を。 |
| カンナ 食いちぎられた心臓から ほとばしり出て 恨みを呑んで凍りついた 血の花よ おまえもまたその血ゆえに 愛する人と結ばれることが なかったのだね 昭和四十八年六月二十一日 |